コトバって奥が深いって思ったことはないですか?
例えば
「springはなぜ春もバネも意味するの?」
「『象は鼻が長い』の主語は象?鼻?」
これに皆さん自信を持って答えられますか?
ちなみに私は初見で無理でした。笑
けど、安心してください!
今回紹介する「ゆる言語学ラジオ」さんのyoutubeを見ればモヤモヤしていた感覚がスッキリ!解決すること間違いなしです!
よくわからなかった上の例である2つについても
最初わからなかった私でも動画を見るだけで「なるほどな〜」と感じることができました!
ゆる言語学ラジオさんの動画からコトバの奥深さを知り
明日職場や友達にぜひ話してみてください!
ゆる言語学ラジオとは
今回オススメするYouTubeチャンネルはゆる言語学ラジオです。
「ゆる言語学ラジオ」は水野太貴さんと堀元見さんの2人でやっている、名前の通りゆるく楽しく言語の話をするラジオ型チャンネルです。
水野太貴さん
1995年生まれ。愛知県出身。名古屋大学文学部卒。専攻は言語学。YouTube、Podcastチャンネル「ゆる言語学ラジオ」で話し手を務める。著書に『言語オタクが友だちに700日間語り続けて引きずり込んだ 言語沼』(バリューブックス・パブリッシング)がある。
水野さんは大学で言語学をガチでやっていたそうです。
ゆる言語学ラジオではその経験を活かしさまざまなテーマについて話をしてくれます。
また、水野さんは出版社で雑誌編集者として現在も勤務されています。
堀元見さん
1992年生まれ。北海道札幌市出身。慶應義塾大学理工学部情報工学科卒。株式会社pedantic代表。YouTube、Podcastチャンネル「ゆる言語学ラジオ」で話し手を務める。著書に『教養(インテリ)悪口本』『ビジネス書ベストセラーを100冊読んで分かった成功の黄金律』がある。
堀元さんは、知的ふざけコンテンツを作り散らかして生活しているそうです。
2本の動画紹介
言語学と聞くと
- 難しく感じる
- いろいろな言語を話すことができる
と誤解されがちですが
簡潔にまとめると「言語学は特定の言語を習得するのではなく、言葉という現象そのものの原理や構造、そしてその奥深さを解き明かそうとする学問」だそうです。
それでもみなさんの頭の中では「?」とイメージしにくいですよね笑
具体的に2本の動画を紹介していきます!
春とバネ、なぜ両方springなのか-多義語パズルへの招待
動画はこちら「春とバネ、なぜ両方springなのか-多義語パズルへの招待 #12」
動画の概要
英単語の語源に焦点を当てている動画です。
具体的には、“term”、”present”、”spring” といった複数の意味を持つ単語を取り上げ、それぞれの語源がどのように様々な意味につながっているかを考察しています。
日本語の単語や概念との比較も行いながら、語源を知ることで単語を効率的に覚えられること、そして言語の奥深さや共通性が解説されています。
springはなぜ春もバネも意味するの?
「spring」という単語が「春」と「バネ」の両方を意味する理由について、ソースには以下のように説明されています。
- 「spring」の語源は、もともと「跳ねる(はねる)」というイメージから来ていると考えられてます。
- この「跳ねる」という基本的な意味から、多様な意味が派生しています。
- 「バネ」:これは「跳ねる」という動作そのものと直接的に関連しています。
- 「春」:これは、木の芽や花が土から「吹き出す」というイメージ、つまり勢いよく現れる様子から派生したものです。
- 「泉」:水が地面から勢いよく「吹き出す」様子から「泉」という意味も持ちます。
これらの意味は、「spring」が全体として「生命力がある感じ」や「生き生きとしている」という語源的なイメージを持っていることと関連しています。
さらに興味深いのは、日本語においても同様の関連性が見られる点です!
木の芽が「噴き出す」ことと、泉が「吹き出る」ことの両方で、日本語でも「噴く」または「吹く」という同じ動詞が使われていますよね。
英語と日本語という違う言語にもかかわらず両方で、地面から何かが勢いよく現れる様子を同じように捉え、表現しているという類似性を示しています!
「象は鼻が長い」の謎-日本語学者が100年戦う一大ミステリー
動画はこちら「『象は鼻が長い』の謎-日本語学者が100年戦う一大ミステリー #10」
象は鼻が長いの主語は?
日本語には、「これは主語かな?どうかな?」と、長い間(100年以上も!)たくさんの日本語を研究している学者が「んー、よくわからないぞ!」と悩んできた文がいくつかあるそうです!
特に有名なのが、この3つの文です。
- 「象は鼻が長い」
- 「僕はウナギだ」 (レストランで「ご注文は?」と聞かれて「僕はウナギだ」と言うような場合)
- 「こんにゃくは太らない」
これらの文で、みんなが「えーっと、誰(何)がこの文の主人公(主語)なんだろう?」って、すごく悩んだみたいです。
これまでの考え方(ちょっと難しいなと思ったこと)
昔から、いろんな日本語学者たちが、これらの文を説明しようと頑張ってきました。
- ある先生は、「象は鼻が長い」みたいに、主語が2つ重なってるんだ!と考え
- みんなが学校で習う文法(橋本文法)では、「象は」が主語で、「鼻が長い」が述語(説明する言葉)で、その「鼻が長い」の中にもまた「鼻が」という主語がある、と考えられました。でも、これでも「ん?」って思う人がいました。
- 「僕はウナギだ」については、「だ」という言葉が、実は「食べる」とか「演じる」とか、いろんな意味を隠しているんじゃないか、という考えや、「僕はウナギが食べたい」という文が、色々な言葉を省略して「僕はウナギだ」になったんだ、という考えも出ました。
- 「こんにゃくは太らない」も、「人が太らない」という言葉が省略されたのかな?と考えられたこともありました。
でも、どれも「うーん、なんかピンとこないなぁ」「納得できないぞ」って感じる人が多かったんです!
それは、英語など、外国の言葉の文法の考え方(「主語」が必ずあるはずだ!という考え)を、無理やり日本語に当てはめようとしていたからかもしれません。
最終的な結論(みかみ先生のすごい考え!)
そんな中、三上章(みかみ あきら)先生という人が、こんなふうに考えました。
- 「主語」なんて、日本語にはいらないんじゃない!?
みかみ先生は、「主語」という考え方は、元々日本語にあったものじゃなくて、外国の言葉の文法の考え方を借りてきただけだ、と言いました。
だから、無理に「主語」を探さなくてもいいんじゃないか、と考えたんです。
これが「主語抹殺(しゅごまっさつ)」という、ちょっとかっこいい名前の考え方です笑
- 「は」は「誰(何)について話すか」を決める!
みかみ先生は、「〜は」の「は」という言葉は、「主語」ではなくて、「これから、このことについてお話ししますね!」という「主題(しゅだい)」や「トピック」を決める言葉だと考えました。
- 例えば、「私は〜」と言うと、「今から私について話すぞ!」って、私に注目が集まるイメージです。
- そして、一度「は」で注目を集めると、その話の終わりまで、ずっとそのもの(人)が特別な存在(主題)として続くんです。小説の「吾輩は猫である」の「吾輩」が、物語中ずっと主人公であるようなもんです。
- 「が」と「は」は、全然違う種類の言葉なんだ、とも言っています。
- これで全部すっきり! この「主題」という考え方だと、今まで難しかった文も、すっきりと説明できます。
- 「象は鼻が長い」 → 「象についてお話しますね。その象の鼻が長いんですよ」「こんにゃくは太らない」 → 「こんにゃくという食べ物について話しますね。それは太りませんよ」
- 「僕はウナギだ」 → 「僕のことについて話しますね。それはウナギです(この場合は、ウナギを食べたいという意味ですね)」
- このように、三上先生の「主語をなくす」という考え方で、日本語の「は」が持つ特別な働きがよくわかり、長い間謎だった日本語の文が、もっと分かりやすくなった、という訳です!
まとめ
今回おすすめしたYouTubeチャンネルはゆる言語学ラジオです!
水野太貴さんと堀元見さんの2人でやっている、名前の通りゆるく楽しく言語の話をするラジオです
- 「springはなぜ春もバネも意味するの?」
- 「『象は鼻が長い』の主語は象?鼻?」
などの身近なトピックから、コトバの奥深さを感じることができましたか?
「言語学の二歩くらい手前の知識が身につくラジオ」を目指しており、YouTubeとPodcastで配信中です。
言語大好きで言語オタクの水野さんと様々なジャンルの知識があり話し上手で聞き上手?な堀元さんのトークが見どころです。ぜひYouTubeで動画も見てくださいね。
参考文献
動画の参考として挙げられていた書籍を紹介します!気になった書籍があればぜひ読んでみてくださいね。
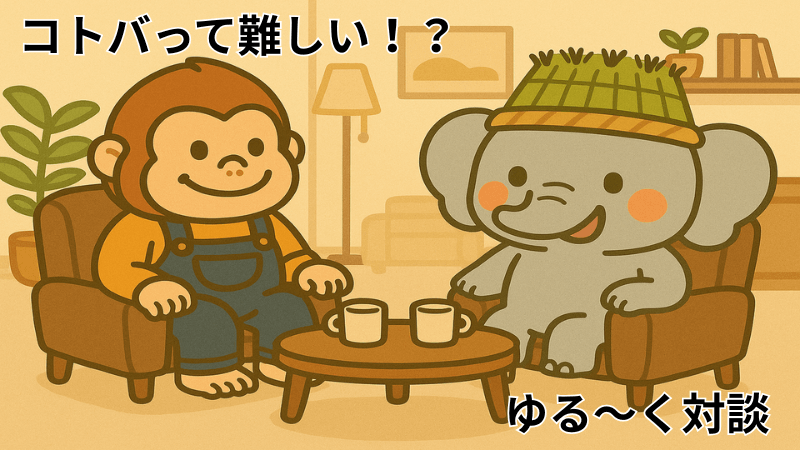

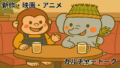
コメント